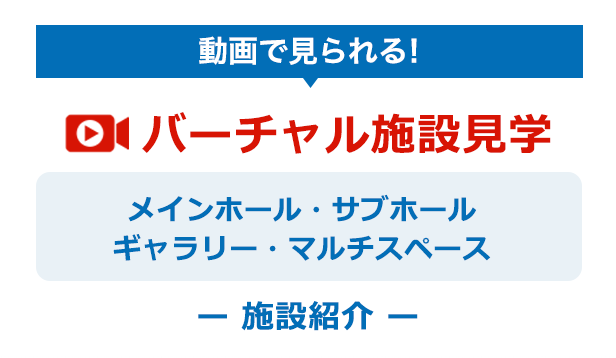●味方玄さん インタビュー
全文公開用_味方先生インタビュー.pdf
―――― 今回の公演で初めて能・狂言に触れる方、初めて見てみようと思っている方に向けて、能の魅力や面白さ、鑑賞ポイントをお教えください。
鑑賞のポイントの一つは、「わかっている言葉を聞いて、想像をするということ」ですね。
たとえば、「あの武庫山颪弓弦羽が嶽よりも吹き下ろす嵐」や「海床の体が荒ろうなった」という台詞があります。それは「海が荒れて、風が吹いて、船が進みにくいよ。」ということですね。だから、舞台上には作り物の簡単な船の装置が出ているだけですけれども、その台詞を聞いて「波が高くなってきた」とかを想像するんです。
ほかにも「主上を始め奉り一門の月卿雲霞の如く。波に浮かみて。見えたるなり」という、難しい台詞もあります。これは、平家の亡霊たちが波に浮かんであらわれてくる様子を表していますが、舞台上には、平知盛一人しかおりません。
お客様が、平知盛の後ろに海に沈んだ平家の一門がダーッと出てきて、亡霊たちが源義経に襲い掛かってくるという絵を想像してもらうと「なんか一人出てきたな」と見えている一人ではなく、沈んだ人たちの中の一人が平知盛であるというのが見えてきます。
歌舞伎であればセットがあって、布で波を作ったりするんですけどね。能の場合それがない分、百人見ていれば百様の波ができるわけです。どういう風に想像するかっていうのが、面白いんです。
―――― 想像が公演を楽しむポイントということですね?
そうですね。同じものを見ても、人それぞれ感じ方が違うというのが能の面白いところです。年を重ねた方が能を楽しいと思えるのは、「月」をとってみても、60年生きていたら60年分の月を見てきて、60回四季を経験しているわけで。20歳の人は感受性が強いけれども、20年分の月しか見ていなくて、20回しか四季を経験していない。経験値が豊富ということは、それに即した記憶や経験から想像のものを引っ張り思い浮かべられるのが、長く生きている人なんです。悲しいことがあった時に見る月と、嬉しいことがあった時に見る月とでは捉え方が全然違うように、心の動きが能にはあるんです。同じ演目でも、各年代で違う受け取り方をするし、演じる側も30代と50代ではまた違うんです。静御前と源義経の別れにしても、単に恋人同士が別れるんではなく、いろいろな情景を想像し思い浮かべられることが、面白さにつながっているかもしれません。
使い古された言葉で「一期一会」というのがありますけれど、本当にその通りで、その一日しかないというところに、見てもらう価値があるんです。
―――― 今回の番組の特徴や取り上げた理由を教えてください。
まずは、能の「船弁慶」はとても分かりやすい題材であるということ。皆さんの知っているヒーロー源義経・ヒロイン静御前が登場する。しかも、源義経は子方で登場するのが能の面白いところで、源義経と静御前といった時に思い浮かべる大人が演じるようなものとは違い、色ごとにならないように子どもが演じるというのが特徴です。
もう一つは、初めてシリウスの舞台で能がかかるということで、格式のある番組としました。神・男・女・狂・鬼といって、神様のもの、修羅もの、女もの、狂いのもの、鬼のものという番組を立てるのですが、今回は、冒頭に「神歌」、修羅もの「屋島」、女もの「羽衣」、狂言「佐渡狐」、鬼のもの「船弁慶」という番組立てをしています。
―――― 「船弁慶」を見る時のポイントはありますか?
「船弁慶」は、見ていて楽しく難しくないもので、初心者も見巧者も、それぞれに魅力を感じることのできる演目なんです。簡単なものだと、見巧者にはつまらんとなってしまうのですが、「船弁慶」はそういうものではなく、深いんです。
ワキ(弁慶)が出てきて、話を進めていきます。弁慶の言葉で物語が進んでいくのがキーワードとなっているので、それを聞いて場面を捉えていって欲しいですね。主役が出てくるまで待っているのではなくて、最初の場面から最後の場面まで、弁慶は舞台に居続けます。
そして、能には一曲通して起承転結があるんです。常に前のめりに進んでいくわけではないので、眠くなるところも、優雅なところも、激しいところもあります。そういうところは、身を任せてもらって、うとうとする、とか、優雅だな、とかあっても良いんですよ。
そして、音で情景を表す、笛、小鼓、大鼓、太鼓の生のお囃子や、後見が黒子の役なんですけど、堂々と出てきて、堂々と帰っていくんです。そこには、見えていない約束がありますが、こそこそとしたら、空気が動いて余計に目立つから、ちゃんと紋付を着て登場人物と同じように、普通に来て、普通に帰っていくのが能の光景なんです。お囃子も背景として、ビジュアル的にも重要で、物をとるとか、構えるとか、全部が型なんです。見ていて楽しいと思います。
―――― 「仕舞」の見どころはありますか?
「船弁慶」と少し被るのですが、「屋島」の主人公は源義経です。平家との闘いで義経が屋島で手柄を挙げた武勇談が、昔から持て囃され、戦に勝ったという部分から、お正月などでめでたい演目として取り上げられ、演出も施されました。これが修羅ものといって武人がシテのもの演目です。「羽衣」は天女を題材にしたもので、優美な内容です。この二つは、お正月にふさわしいめでたい演目です。
そして仕舞は、略式の演奏方式で、能の一部をやるため、囃子も入れずに紋付袴で行います。役者の個々の魅力やスタイルが見られるデッサンみたいなものです。色彩全部を重ねるのではなく、その人の骨格や構えが良く見え、とても見やすいです。
―――― 今回の出演者の魅力をご紹介ください。
この世代の一番ではなく、この能楽界のトップの人たちです。一番華があって、一番魅力のある年代で、一番熟している方々だと思います。
―――― 今回使用される衣装についてご紹介いただけますか?
「道成寺」なら鱗模様、「猩々」なら青海波など、身に付ける衣装に決まりがありますが、「船弁慶」では、決まりの衣装がありません。着付け・袴などのパーツは決まっているのですが、役者のその日の取り合わせ(コーディネート)に任されているんです。静御前は「かわいいのか、おしゃれなのか、スマートなのか、お姉さんなのか」、知盛も「品があるのか、野性味を帯びているのか」。などの人物設定でも変わってきます。でもそれは「秘すれば花」といって、言わないんですよ。
―――― 舞う時に工夫していることや苦労していることはありますか?
お客様に想像していただくためにも、説明してしまうのは良くありません。例えば、悲しいから目をつぶってしまうのではなく、役者の動きや能面の照り曇りの角度によって頬を伝う涙なのか号泣しているのかを、お客様に想像してもらうことが大切で、泣いていますっていう説明をしてしまうのは興醒めになってしまいます。
そうならないように演技せよというのが世阿弥からのセオリーです。それなので、説明的な大げさな表現はせずに、心へ響くように演じています。
―――― 能楽師ならではの職業病のようなものはありますか?また、能以外で趣味はお持ちですか?
たとえば、電車で立っている時でも、構えをしてしまいます。腰を返して、首を伸ばして立ってしまっている。ただ、その日常が舞台に出ますから。舞台だから構える、楽屋だからオフだというわけではありません。
演じるという場合は、その役になりますけど、後見とか地謡とかは舞台に出ていて常に座っています。舞台だから、楽屋だからといった違いはなく、そういう心掛けを大切に思っています。
なので、全部が能に繋がっていると思います。古美術とか、映画をみるとか、演劇を見るとかにしても、見ていて、ああいう風にしたらいいな、こういう風にしたらいいな、とかって繋がっていきます。
僕は能フェチなので、オフは切り離してとか、飲むときくらい違う話を、とか嫌いで出来ないんです(笑)
―――― 日本以外でも上演されているかと思いますが、違いはありますか?
日本よりも、ストレートに感じてくれているような気がします。日本人はまず聞き取ろう、意味を理解しよう、ちょっと勉強してから行こう、ってなるんですけど、そういうのがなく会場にいらっしゃいます。そして、自分の感想に自信を持っていますね。「ここはわからない!」とか、「ここは素晴らしかった」など。日本人は、わからなくても、わからないのはおかしいと思って、わかるふりをしてみたり、みんなが良いって言うから良いって言ってみたりする気がします。それに対して海外の公演では、すごくピュアな気持ちが伝わってきますね。舞台の空気感、客席の空気感も含め、外国の人から見たら、出て行って、座って、扇を広げて、っていうすべてが、仕来りの様になって、不思議なんでしょうね。自分のファミリーの家紋をつけて出てくる、日本という独特の文化も面白いと思っているかもしれません。
―――― 年を重ねていくにあたり、能への向き合い方に変化はありますか?
そうですね。年を重ねていくと、それなりに軽い服にしたり、動きやすい着方にしたり、上着を無しにしたり。
僕は、能に関しては、アンチエイジングっていうのはないほうがいいと思っていて、ちゃんと年を取っていかないと、できる演目が限られてしまいます。「西行桜」という、年を重ねていないとできない演目があって、若者が年を作っても演じられず、ちゃんと年とってきた人じゃないと出来ません。
それなりの人生経験を積んで、骨格にしても作るのではなく自然なところが人の魅力になってくるんですね。かすれ声も、かすれさせるのではなく、精いっぱいやって、かすれてしまう、というところが能の究極の見せどころです。それでも心に花があるという、どこかでいいと思うのが世阿弥のいう「老木に花の咲かんが如し」という、魅力の最終形になるんです。年齢に抗うのではなく、どういう風に演じるかっていうソフト面を充実させるようになってきました。
―――― 公演を楽しみにされているお客様へメッセージをお願いいたします。
生で見たことのない方に、一度、触れて見て欲しい。劇場で実際に感じて見て欲しいんです。一度この機会に、能というのはどういうものなのか、自分の目で確かめてください。衣装からでも、能面からでも、題材からでも、役者からでも、とにかく来て見てもらって、アプローチを見出してもらえると嬉しいです。
そして、発見がいっぱいあると思います。何にもない舞台から始まって、最後に何にもなくなりますから。
そういった意味では、余韻も楽しめるかもしれません。映画でも、本編終わってエンドロール見て、明るくなる、そんな感じで、役者が引いて舞台だけになるっていうところまで、反芻してもらえたら面白いかなと思います。