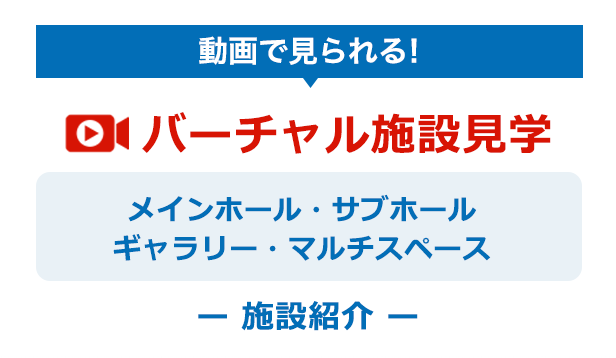未来を担う若者が、伝統芸能に挑戦!
大和市出身の落語家 柳家あお馬氏が講師となり、小学4年生~高校3年生の8名が初めての落語にチャレンジしました。一席披露することを目標に、約1か月のワークショップを実施。落語の面白さや、高座での所作など、短期間でたくさんのことを学びました。「みんなを笑顔にしたい」という、明るく前向きな想いで一生懸命取り組み、成果発表会では、8名全員が堂々と一席を披露。あたたかい笑顔で溢れる最高の寄席を作り上げてくれました。
ご来場いただきましたみなさま、ありがとうございました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
大和市出身落語家・柳家あお馬さんにインタビューをしました。
Q. あお馬さんと大和市の関係は?
大和市の出身で、小学校は林間小学校に通っていました。大学卒業後に一人暮らしを始めましたが、土地勘や住みやすさと条件などが合ったので、師匠に入門するまでは大和市に住んでいましたよ。
Q. 落語を知ったきっかけは?
私が中学生ぐらいの時はお笑いブームで、テレビでお笑いのネタ番組をやっていたんですよ。『エンタの神様』や『笑いの金メダル』などをよく見ていて、お笑いが好きで観ているうちに、なんとなくお笑いのルーツを知りたくなりました。そのなかの一つに落語があったんですね、聴いてみるとこれが面白い。ただ面白くて笑えるものから、泣けるもの、考えさせられるものまで、幅の広さに衝撃を受けたのを覚えています。
Q. 落語を意識しはじめたきっかけはいつですか?
高校生の頃の話になるんですが、毎日部活があって、それが生活の中心になっていたんです。そんな中で部活が終わって家に帰ってきた時間に、落語番組がやっていたんですよ。浅草演芸ホールの寄席をそのまま流している番組だったんですけど、いつしかそれを見るのが、私の中で楽しみになっていったんです。それもあり、学校が休みの日に初めて浅草の寄席に行ってみたんです。その時は「落語をやりたい」という気持ちは無かったんですけど、実際に観て、落語だけでなく、その空間や雰囲気もあわせて「面白いな」って感じたんです。それがちゃんと落語を意識しはじめたきっかけかもしれないですね。
Q. 初めて生で鑑賞した時の感想はどうでしたか?
やっぱり生で見るのは違いますね。生の寄席の照明の当たり方とか、座布団の光沢とか、人の心が躍る場所だったなって印象を持ちましたね。正直、はじめて聴く落語って、その噺の半分ぐらいしかわからなかったんです。でもその場に居て楽しいっていう感覚を持ったんですよね。
Q. 落語を演じることになったきっかけは?
大学に入学したときに、漫才やコントをやるお笑いサークルに入りたかった気持ちがあったんですけど、残念ながらお笑いサークルは無かったんですよね。それで、一番近いサークルが落語クラブ(落語研究会)だったんですよ。そこで落語クラブに入ろうと思ったんですけど、サークルに入るには、落語を一席覚えなければいけないルールがあったんです。「子褒め」か「寿限無」のどちらかを覚えなければいけなかったんですけど、実際にやってみたら、楽しかったんですよね。何しろ、ひとりで出来るし、人とネタ合わせをする必要もないし。落語を演じたのは、その時に覚えたものを先輩の前で披露したのが最初だと思うんですけども、思ったよりちゃんと出来たかな。という印象でしたね。とにかくやってみて「性分にあっているな」という感覚を持ちました。それから、大学の4年間をかけて落語に徐々にのめり込んでいった、という感じです。
Q. もともと人とお話することが好きだったんでしょうか?
ただ話をするというよりは、落語を話すことを面白いと思っていたんですよね。「人と楽しく話す」という延長線上に落語があるのではなくて、落語というスタイルで、古典落語を演じるっていうことが楽しかったですね。純粋に。落語をお客様と一緒に楽しんでいるという感覚も良かったですし、とても楽しかったです。
Q. 噺家へ進むことを決めたきっかけは?
就職活動をする頃から、就職をしようか落語家になろうか、と悩んでいたんですけど、「噺家になりたかったかなぁ」という気持ちを抱えながら社会人になるよりも、噺家をやってみて、ダメなら諦めた方が良いかな、という気持ちがあったので、卒業して2年間ぐらいは、どの師匠に入門しようか、じっくり考えながら過ごしていましたね。この2年間がとても濃密で、今の自分の基礎になっていると感じています。
Q. プロになってからの初めての本番はどうでしたか?
前座になってから、浅草演芸ホールで初めて寄席に出演したんですが、思うように上手くできませんでした(笑)。前座の仕事というのは、場内整理だったり、次の人が高座に上がるときにやりやすい環境をつくったりというのが中心なんです。そして、前座が高座にあがるタイミングというのは、お客様がつっかけている(入場している)最中で、客席がザワザワしているんです。そんな中でとにかく、無我夢中で10分ぐらい披露して高座を降りてきた感じで、本当に何が何だかわからなかったですね(笑)。
Q. 入門されてから今年で10年という節目になりますが、落語の活動を通じて大切にされていることはなんですか?
ご高齢で寄席まで足を運ぶことが難しいという方でも、落語を観たいという方は多くいらっしゃると思うので、こちら側から出向き、落語会の機会を増せればいいなと考えています。これは大和市に限らずですが、落語を楽しんでもらうことによって、その人の中の日常を少しでも彩ることが出来れば嬉しいですし、そういう機会を出来るだけ作っていきたいなと思っているんです。
Q. 今回のワークショップにどんな子ども達に来て欲しいですか?
「落語をやりたい」という気持ちが少しでもある子どもに来てほしいなと思っています。落語はやろうとすれば必ず出来るものだと思いますので、「やりたいけど僕にはできないだろう」というのは、とっても勿体ないです。こちらでしっかりとサポートしますので、安心して応募してもらいたいなと思いますね。「難しそう」「覚えるのが大変そう」と感じている方もいるかとは思いますが、人それぞれにあったやり方があると思っています。落語を一席話せるようになると、特技としても言えますしね(笑)。
Q. 今回の落語ワークショップへの想いは?
「どんな子どもたちが応募してくれるんだろう」とワクワクする気持ちと、ドキドキする気持ちの両方があります。「どうしたら子どもたちに落語を楽しく感じてもらえるかな」「本番に向けてやり通してもらえるかな」という事を、細かにイメージして、本番につなげていくというのが私の役割だと思っていますし、寄席として成立させるところまで、しっかりとサポートしていこうと思っています。
落語を聞くことや、やることはとても楽しいことで、やりがいがあることなんです。ただ、人に喜んでもらうところまでレベルを上げるのは、実はとても大変なことなんですよね。でも今回は、落語で人を喜ばすまでの「やり通す力」や「やり抜く力」を、落語を通じて養うというか、大切に磨いてもらいたいですね。やり通した後は、感動が必ず待っていると思うので、それを一緒に味わいたいですし、そこを目指して参加者全員で取り組んでいければと思います。