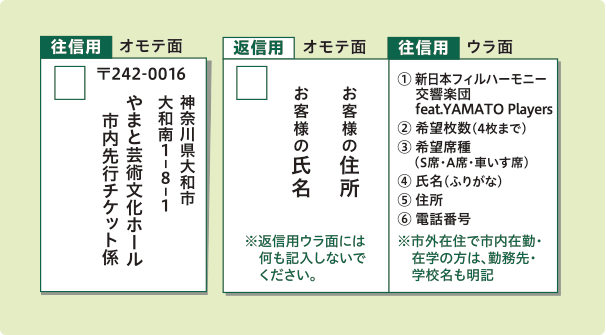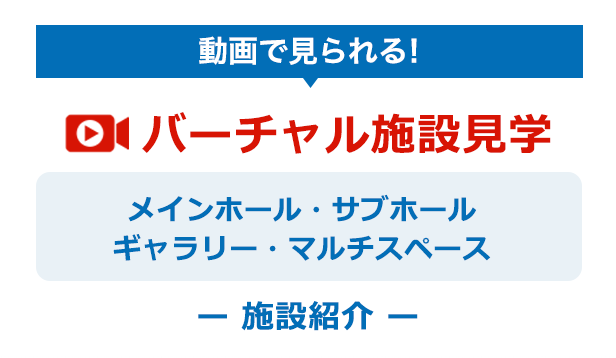出演者インタビュー【全文】

Q.演奏する曲について教えてください。
石井楓子「ピアノ協奏曲 第1番(チャイコフスキー)」
やまと芸術文化ホールの主催公演では、オーケストラのクラシックコンサートが久しぶりと伺ったので、誰もが知っているような有名な作品をお届けしたいと思っていたんです。私はドイツとスイスに留学していたので、 そちらの方の曲を弾くことが多いのですけれど、実はロシア音楽にも思いが強くて。この曲は、ちょうど私が 20 歳ぐらいの時に初めて弾いたんですけれど、留学前だったということもあり、まだ腑に落ちてないところもありました。それから 10 年以上経ち、この機会に、 この思い出深い憧れの曲を地元大和で弾けたらいいなと思ったのが、選曲の大きなきっかけです。オーケストラとピアノが波のように一体になる感覚というのは、ロシアのピアノ協奏曲の良さだと思っています。留学中はロシア奏法を受け継ぐ先生に師事しており、そうして学び直したことでいろいろと感じたこともあります。室内楽的な対話というよりも、ぶつかっていくというか、ある意味、戦いのようなところもあったりして、弾いていても聴いていても面白いですね。この曲を知っている人も知らない人も、迫力を楽しんでいただけるのではと思います。演奏するのが楽しみです。
佐藤和彦「テューバ協奏曲(ヴォーン・ウィリアムズ)」
テューバって、多分皆さんの認識としては、ピアノやチェロのような立派にソロ楽器として認識されている楽器と同じように演奏することは珍しいというか、変わり種みたいな感じだと思います。実は、今回のヴォーン・ウィリアムズのコンチェルトを新日本フィルと共演するのは4回目で、何かにつけてやっていて。これしかないんじゃないかな?という感じで選曲しました。ピアノやチェロと比べると、テューバのコンチェルトは少ないですが、その中で一番の名曲です。だから、毎回その貴重なコンチェルトをやらせていただけるのは嬉しいですね。聴きどころなんですけど、特に二楽章のロマンツァが、弦楽器との音色のブレンド感がすごく魅力だと思うんですよ。テューバは、普段のオーケストラでの役割としては下から支えている楽器で、仲間の金管楽器と一緒に音色を作ることには慣れているんですけれど、弦楽器とは音の出し方が全然違うということもあり、音を上に乗せていくというのが、普段から苦労するところなので、それができた時にはすごく達成感がありますね。そういう音色のブレンド感を感じてもらえたら嬉しく思います。
遠藤真理「チェロ協奏曲(ドヴォルザーク)」
チェロと言ったら、このドヴォルザークのコンチェルトが本当に有名ですし、このコンチェルトがあることによって我々チェロ奏者も救われるというか。チェロってどうしても周りの音に馴染んでしまうところがあって。ヴァイオリンは音が高いので飛びますし、ピアノはオーケストラとは音の質が違うし、管楽器は管楽器ですごく音が通りますから、そういう意味でチェロってすごく不利だなと思っていました。ただ、自分がオーケストラで弾くようになってみて、このドヴォルザークのコンチェルトのオーケストラの充実感が、本当にシンフォニックに書かれていると感じて。特に木管楽器が大活躍しますし、木管とチェロのソロの対話が、室内楽的にもすごくよく書かれているので、そこを聴いてほしいなと思います。オーケストラとの対等な語り合いっていうのがすごく魅力だと思っています。チェロは音域が広い楽器なので、高音域から重低音まで「こんないろんな音が出るんだ」というところも、ぜひ感じていただけたら嬉しいです。
松村秀明(指揮)
普段クラシック音楽を聞かない人でも、きっと楽しめるプログラムです。チャイコフスキーは超名曲で盛り上がると思いますよ。オーケストラとピアニストがバン!って、いい意味で競争するというか、ぶつかるという。それは本当に生で聴いていないと分からないし、その熱量が伝わらないと思う。ヴォーン・ウィリアムズは、イギリスらしいエレガントな部分が素敵ですよね。佐藤さんがおっしゃっていた二楽章も、ぜひじっくり聴いてもらいたいです。ドヴォルザークも本当に名曲で、遠藤さんもおっしゃっていた通り対話的。日本人に合うという言い方がふさわしいか分からないですが、メロディで使う音が我々にしっくりくる部分があって、懐かしさも感じますね。そういったところを楽しんでもらえたらと思います。
Q.演奏にあたって気にしていることはありますか?
松村:ヴォーン・ウィリアムズは、僕は今回初めて指揮をするんですけど、やっぱりオーケストラの団員がコンチェルトのソリストをやる時のオーケストラの響きって、何かが違うんですよ。「オーケストラでこんなにあたたかい音が出せるんだ」って、いつも思うんです。普段の新日本フィルもすごく素敵な音なんですけど、多分その時とはまた違う、佐藤さんの人柄が引き出す響きが出るんじゃないかなと思っています。
遠藤:ご自身ではどう感じていますか?
佐藤:やっぱり、なんか安心するというか。普段助け合っている分、同じように助けてくれるんじゃないかなという安心感がありますね。
遠藤:そうなんですね。逆なのかな?と思って。みんながソリストとして、後ろから見ているわけじゃないですか。いつも後ろから見ている立場がこう、前に来た時の見え方というか。ヴァイオリンってこんなによく聞こえるんだ、とか。見え方が違うと逆にこう、ドキドキするのかな?って。
佐藤:そうですね。まあ慣れないっていうのはありますね。やっぱり、普段は前で演奏しないし。指揮者も隣にいるっていうね。いつもはこう、ちょっと見えにくいなぁ、っていうのがあったりするのがね(笑)。距離感が違うって。まあ、そこは慣れないというのはありますけどね。普段と役割が全く違うというのもあって。低音楽器って、特にテューバなんていうのは盛り上った時しか出てこないんですけど、結構影響力が強いんですよね。普段はオケを引っ張っていくっていう役回りだけど、ソリストになるとそうはいかなくて。自分一人でいつもみたいに力ずくではいかないんだなっていう。だから、みんなに乗っかって任せるっていう感じが普段と違う。その辺は、ソリストとしての役割というところで戸惑う部分はありますね。
遠藤:私は、オケだと、自分が率先していくとどうしても速くなっちゃうんですよね。アタックとかが。なので、どちらかというと、気持ち的には耳を後ろに向けるじゃないですけど。たとえば木管だったらファゴットと大体一緒だし、金管だったらテューバとトロンボーンと一緒のメロディを弾くことが多いので、その辺の低音域にはすごく後ろにアンテナを張っているんですけど、ソロを弾く時っていうのは音域も全体的に高いし、視線が変わります。座り方も違うし、全部違うと私は思うんですけど、そんな話を友達にすると、「いや、一緒だよ。」って言われてしまうんです(笑)。だから人それぞれなのかなって。私の場合は、ソロで弾かせてもらう時と、オケ中で弾く時と、全然やることが、仕事が違うと思っています。
石井:私も室内楽やリサイタルやコンチェルトなど、いろいろなジャンルで演奏していますが、どれも全然演奏の仕方は違うんですよね。コンチェルトでは周りの音を聴きつつ前に出ていく必要があるのですが、 オーケストラパートを活かしつつ、ダイナミックにソロパートを演奏するためには強い解釈や意志の力が求められていると感じます。
松村:コンチェルトっていうのはソリストありきで書かれた曲なので、ソリストとの対話をしっかりとしたうえで、曲全体を一つのまとまりある演奏になるように構築していけるのが、指揮者としての理想だなと思っています。
Q.大和への思いを教えてください。
遠藤:私は今、家族と一緒に大和に住んでいて、子どもたちも大和市の学校に行っているので、その学校関係の人も目に留まって来てくれると思うんです。私の子ども達が行っている学校ですごく感じるのは、大和は文化への意識が高いなって。子どもの友達が家に遊びに来た時に、「え、ママ楽器弾いてるの?聴きたい!」なんて言ってきたりするんですね。そういうのを見てると、みんな音楽が好きなんだなとか、興味があるんだなって。一方で、あまり学校で授業以外に音楽を体験できる機会がないんですよ。それがすごく残念なので。こういう機会に、場所も近いし、興味のある子たちが気軽にコンサートに足を運べたらいいですよね。「シリウス行ってくるわ」「いいね、近いね」なんてね。やっぱり生音を肌で感じるとか、オーケストラをみて「こんなにたくさん楽器があるんだ」って発見する、すごくいい機会だと思って。
佐藤:僕はずっと子どもの時から大和市で育って、テューバは部活で始めたんですが、そういった大和市での経験がなかったら、今はやってなかっただろうな、ということばかりで。シリウスのすぐ裏に僕のピアノの先生の家があって、この辺は子どもの時から通っていたので、まさかこんな立派なホールができると思ってなかったんです。まだ、こういうホールができる前までは、大和市で自分が演奏家として何かできるなんて想像もしていなかったんですけど、ここ数年ありがたいことにそういう機会をいただけて、恩返しみたいなことができるといいかなと。やっぱり、せっかくこういうホールがあると、文化的にもどんどん向上していっていると思うので、何かそのきっかけになったらいいなと。僕のことを子どもの時から知ってる人はもちろんですが、高校生の時とかに全然関わらずクラスも一緒にならなかった同級生とかも、「なんかやるんだって?」と偶然にもこの公演情報を見て連絡してくれたり、新たな繋がりができたりして。そういった、いろんな繋がりが生まれればな、という気持ちでいます。
石井:私は生まれが南林間で、両親もピアノ教師ですので、普段から地元のお子さんたちと関わったり、 私もその様子を見てきたんですけれども、そういったお子さん達は音楽や文化にすごく興味はあるんですが、都心のコンサートだとちょっと行きづらいこともあるんです。 でも、このシリウスができてから、だんだん 「コンサートに行ってみる!」っていう子たちが増えてきて。私も機会があれば名曲を弾いて、聴いてもらったりして、 刺激になればいいなと思っているんですけれど、やはり今回のように、素晴らしいホールでプロのオーケストラとの演奏を聴いてもらえたら、とても嬉しいなと思っています。以前は大和市内でコンサートするとなった時に、どこがいいのかなと悩むことがあったので、だいぶ環境が変わってきた数年だなと感じています。この 12 月に向けてぜひ市内の方々にお知らせできたらなと思っています。
松村:僕は大和市ではないのですが、実は神奈川県民で小田急線沿いに住んでいて。中高校生の時は湘南台まで通ってたので、個人的にはなんだかすごく近い居場所って感じがして。なので、僕も仲間に入れてほしいです(笑)!シリウスは人がたくさん出入りするのがとてもいいところで、重要なところだなと思って。ホールで演奏会がなくても人がいて、そこでこういうチラシを見たり、普段コンサートホールに行かない人にも来てもらえるチャンスだと思うので、そういう人が聴きに来た時に、来てよかったなって思ってもらえるような演奏ができたらと思います。
Q.お互いへの印象や当日の演奏で楽しみなところはありますか?
佐藤:チェロのドヴォルザークは、もう何度やったか分からないぐらいよくやる曲なので、オケ中でも演奏したいなと思いつつ、あのメロディーをテューバで吹いたら気持ちいいだろうなと思ったり。この曲のテューバも実は結構シビアだったりするんですよね。いいところも難しいところも全部含まれていて、憧れの曲っていうか。ピアノのチャイコフスキーは編成にテューバが入ってないんですよね。なので、そういう時は裏でみんなの演奏を聴きながら、夢心地っていう感じですね。
石井:私は低音楽器が特に好きで、弦楽器はチェロが好きですし、コンチェルトを演奏していても、オーケストラで低音が迫力をもって響くところがたまらないと思っています。チャイコフスキーのコンチェルトは残念ながらテューバはないのですけれど、金管楽器の華やかな音が素敵で。 遠藤さんも佐藤さんも、 オーケストラの経験もソリストの経験も本当に大先輩でいらっしゃいますので、 リハーサルも楽しみですし、いろいろな新しい発見を私も経験させていただきたいです。
遠藤:お二人と話しているだけでも、本当にお人柄が見えるといいますか。大和の自然の中で育たれて、いい環境だったんじゃないかなと思うんですよね。大和は自然が身近にありつつ、それでいてちょっと足を伸ばせばすぐ新宿も行けますし。山にも囲まれて、うちからちょっとだけ富士山も見えるんです。そういった中で、音楽をのびのびやってこられた方々なので、緊張感はありつつ、素晴らしい演奏をされるのではないかと思います。
Q.ご皆様へメッセージをお願いします。
松村:3名のソリストの素晴らしい演奏をぜひお楽しみください!この3名の演奏が聴けて良かったね、と思ってもらうのと同時に「やっぱ、いい曲だったね」と思ってもらえたらすごく嬉しいです。オーケストラが初めての方もいるかもしれませんが、絶対に楽しめると思いますし、ステージのキラキラしている感じとかも体験できると思います。新日本フィルの雰囲気は、本番になると、パッてステージが明るくなるようなイメージが僕にはあるので。年末を飾る新日本フィルの華やかなキラキラした雰囲気も味わってもらえたらなと思います。皆さんの五感を使って、素晴らしい音のシャワーを浴びて欲しいです。
石井:チャイコフスキーというと、『くるみ割り人形』が有名かなと思うのですけれど、子供も大好きなチャイコフスキーの人気というか、人の心をつかむ魅力というのをすごく感じています。このピアノ協奏曲は、出だしはとても有名ですが、その後はあまり知らない方もいるかもしれません。この曲は、非常に物語性があり、幻想的で、広大な大地を思わせる抒情詩のようなところがありますので、そういったところを全曲通して聴くことでぜひ楽しんでもらえましたらと。チャイコフスキーの素晴らしさをぜひお伝えできましたらと思っています。
遠藤:チェロという楽器を意外と間近で見たことない方もいると思うので、オーケストラに対峙するソリスト楽器としてのチェロを見て欲しいとは思いつつ、オーケストラ全体の色彩が豊かなサウンドも楽しんでもらえたらと思います。よく、「室内楽とオーケストラって何が違うんですか?」と聞かれることがあって、人によっては大きな室内楽がオーケストラだと思っている人もいるんです。間違ってはいないけど、なんと言っても指揮者がいることが一番の違いで、指揮者の存在ってすごく大きいということを、聴いてる方も感じるんじゃないかなと思います。どうしてこう振ったら音が出るのだろうとかね。そういうところは、生で見ることでその空気感とか呼吸とかが聞こえてくるので、そういうところを楽しんでいただきたいと思います。
佐藤:今回、本当に素晴らしいソリストとご一緒する中で、新日本フィルを代表するわけじゃないですけど、大和市出身として、架け橋のような感じになれたらいいのかなと思っています。今回は、名曲コンチェルト揃いのプログラムで、オーケストラだけの曲がないのですが、今回のコンサートをきっかけに、オーケストラを、新日本フィルをもっと聴いてみたいな、新日本フィル素敵だなっていう大和のお客さんが増えてくれたら、大和市出身の演奏家として、すごく嬉しいなと思っています。